
小幡正敏(おばた・まさとし)
OBATA Masatoshi
- 専門
- 社会学
Sociology - 所属
- 教養文化・学芸員課程
Humanities and Sciences / Museum Careers - 職位
- 教授
Professor - 略歴
- 2004年4月着任
1958年静岡県生まれ
早稲田大学大学院 文学研究科博士後期課程
(社会学専攻)単位取得退学(修士) - 研究テーマ
- 現代社会における個人化と統治。贈与の現代的可能性。
著訳書
- 『社会学の視角』武蔵野美術大学出版局、’25年。
- 『見知らぬ者への贈与』武蔵野美術大学出版局、'23年。
- 『社会学のまなざし』武蔵野美術大学出版局、'04年。
- 田中滋子編『地域・家族・福祉の現在』まほろば書房、'08年(分担執筆)など
- 田中・荻野編『社会調査と権力』世界思想社、'06年(分担執筆)
- 渋谷・空閑編『エイジングと公共性』コロナ社、'02年(分担執筆)
- 児玉幹夫編『社会学史の展開』学文社、'93年(分担執筆)
- 井上・坂田編『おもしろ社会学』学文社、'93年(分担執筆)など。
- A.ギデンズ『社会学 第5版』而立書房、'09年(共訳)。
- A.ギデンズ『国民国家と暴力』而立書房、'99年(共訳)。
- U.ベック、A.ギデンズ、S.ラッシュ『再帰的近代化-近現代における政治、伝統、美的原理』而立書房、'96年(共訳)。
- A.ギデンズ『近代とはいかなる時代か』而立書房、'93年(共訳)。
- K.E.ボールディング編『ヒューマン・ベターメントの経済学-生活の質へのアプローチ』勁草書房、'89年(共訳)など。
Professor of Sociology. His main research interest lies in the sociology of risk society, with a particular focus on “Individualization”, “Governmentality” and “Gift” in contemporary societies. He published a number of papers concerning “ neoliberal forms of governance in Japanese society”. He also published some books: Shakaigaku no shikaku (Sociological point of view, Musashino Art University Press, 2025). Mishiranu mono eno zouyo (Giving to strangers:Sociological Essays on Gift and Security, Musashino Art University Press, 2023). In addition, he translated several works of contemporary social theorists : U.Beck, A.Giddens, S.Lash, Reflexive Modernization: Politics, Tradition, and Aesthetics in the Modern Social Order. (Saikiteki Kindaika, Jiritsu Shobou, 1996), A.Giddens,Nation-States and Violence. (Kokumin-kokka to bouryoku, Jiritsu Shobou, 1999).
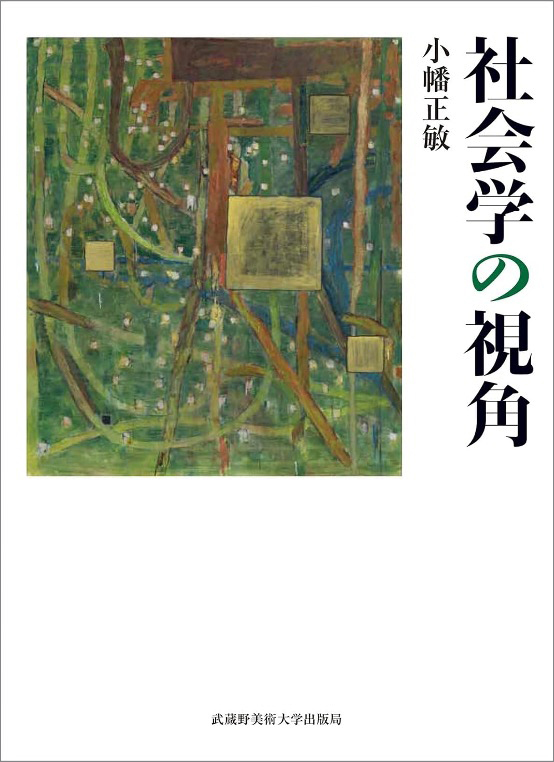
『社会学の視角』
武蔵野美術大学出版局、2025年
初学者向けに書かれた社会学のテキスト。教科書というよりエッセイ集のような形を取っている。
なぜ19世紀に社会学という“視角”が生まれたのか。その“視角”は大きく変容しつつある21世紀の現代においても有効性を失っていないのか、などを論じた。マルクス・デュルケム・ウェーバーら社会学(社会思想)の始祖たちの思想に始まり、戦争とトラウマ、贈与と交換、近代家族の変容、社会保障の持続可能性、フォーディズムとポストフォーディズム、都市とは何か、テクノロジーと社会、グローバリゼーションの功罪、フェミニズムの意味、マイノリティ差別撤廃運動、アートと社会運動など、いろいろなテーマが詰め込まれている。2004年刊行『社会学のまなざし』の増補改訂版。
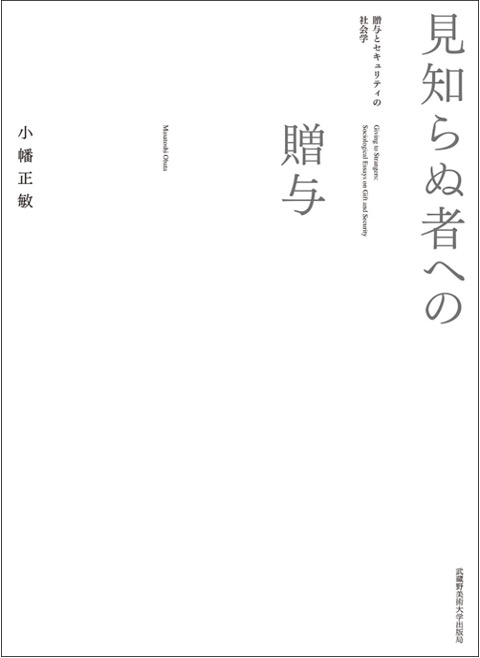
『見知らぬ者への贈与―贈与とセキュリティの社会学』
武蔵野美術大学出版局、2023年
これまで散発的に書かれてきた文章をまとめた論文集。副題にあるように、テーマは現代社会における「贈与とセキュリティ」。他者に何かを贈る、受け取る、お返しをする―この一連の行為を、われわれ人類は太古の昔から繰り返してきた。“贈与”という出来事の不思議さと、現代的可能性を論じてみた。
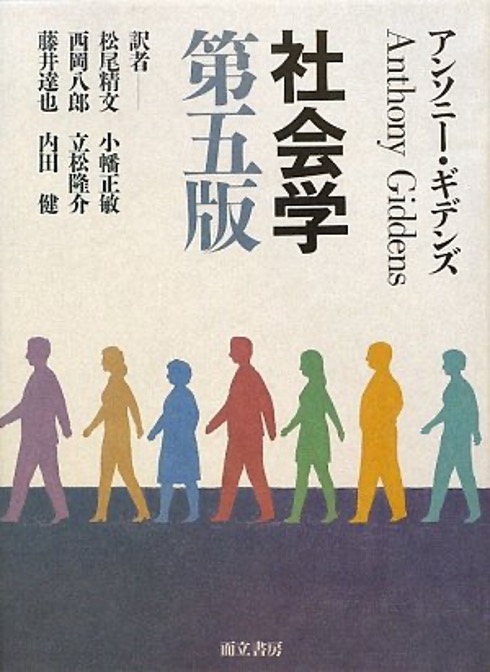
『社会学 第5版』
アンソニー・ギデンズ
而立書房、2009年(共訳)
現代イギリスの社会学者アンソニー・ギデンズによる世界的に知られた社会学テキストの日本語訳[原著2006年刊]。1992年の邦訳第1版から2009年の第5版まで、原著の改訂ごとに改訳を重ねてきた。テーマの幅広さ、シャープな記述、たびたびの改訂による内容のアップデートなど、これまで日本でも多くの読者を得てきた。ただ、改訂と改訳がなされるたび頁数は増え、この第5版では本文だけでも上下2段組で950頁、重量はおよそ1.25キログラム。日本の社会学界隈では、その重さゆえ、鈍器本(どんきぼん)との異名もある。もちろん、凶器としても使える、という意味である。
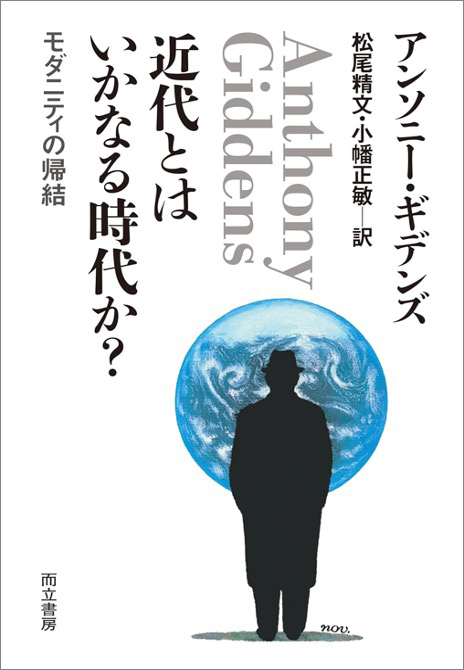
『近代とはいかなる時代かーモダニティの帰結』
アンソニー・ギデンズ
而立書房、1992年(共訳)
同じくアンソニー・ギデンズの翻訳[原著1990年刊]。ポストモダンという言葉がもてはやされていた当時、そもそもモダンとは何かを、ギデンズは、社会学的視点で真正面から論じようとした。安心と危険、信頼とリスク、脱埋め込み、モダニティの再帰性、存在論的安心、ユートピア的現実主義など、刺戟的な概念が次々と繰り出される。訳者として巻末に解説論文(小幡正敏「再帰性と近代」)を付した。
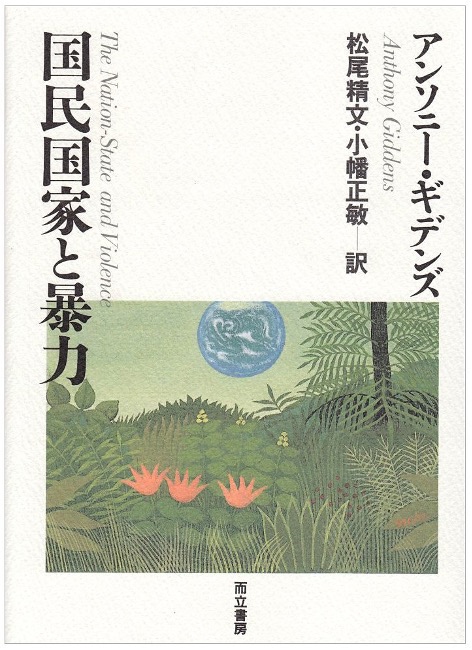
アンソニー・ギデンズ
而立書房、1999年(共訳)
これもアンソニー・ギデンズの翻訳[原著1985年刊]。ギデンズはヨーロッパを代表する社会学系の論客の1人であるとともに、かつて英国のブレア労働党政権のブレーンでもあった。ギデンズはこの本をとおし、国家と資本が現在のような姿になるまでの歴史を、「暴力のコントロール」、「監視と管理の技術」という2つの軸にそって克明に解き明かそうとする。1989年東欧革命以前の本だが、今読んでも古びてはいない。国家と資本というものがいかに凶暴な暴力性をはらんだ怪物であるかが見えてくる。
